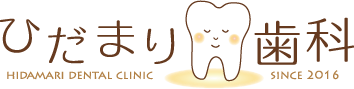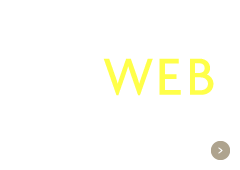「歯肉退縮(しにくたいしゅく)」という現象をご存知でしょうか?
歯を支えている歯茎が何らかの理由で下がる現象で、見た目が悪くなるだけでなく、歯やその周囲にさまざまな症状を引き起こすため注意が必要です。
歯肉退縮が進み、露出した根面は容易に虫歯や歯周病になりやすいことがわかっております。
初めは痛みを伴わず徐々に進行していくため、気づかず放置しているうちに悪化しているケースがよく見られます。
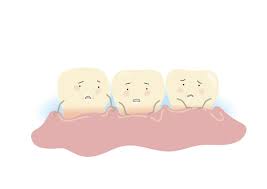
歯肉退縮の原因
歯肉退縮の原因としては、以下に挙げる12の病気や習慣が挙げられます。
原因①歯周病
歯肉退縮の主な原因は歯周病です。歯周病とは、歯ぐきに細菌感染が起こり、炎症反応が生じる病気です。
日本人の成人の約8割がかかっているとも言われており、国民病といっても過言ではありません。
そんな歯周病では、歯ぐきの破壊が起こり、歯肉が下がっていきます。
進行すると顎の骨である歯槽骨(しそうこつ)まで壊されます。
初期症状
- 歯ぐきが赤くなる、もしくは紫色になる
- 歯ぐきが丸みを帯びて膨らんでいる
- ブラッシングをすると出血する
- 慢性的な口臭がある
原因②ブラッシングが強すぎる
毎日一所懸命に歯磨きすることは良いのですが、ブラッシング圧が強すぎると、歯ぐきを傷めてしまいます。
その結果として、歯肉退縮が起こります。
同時に歯の表面を覆っているエナメル質を傷つけることにもなるため、適切な力で歯磨きすることが大切です。
原因③不十分な口内ケア
口内ケアが不十分だと、歯の表面や歯ぐきとの境目に汚れがたまります。
具体的には歯垢や歯石ですね。
それらが細菌の温床となり、歯ぐきに悪影響をもたらします。
原因④歯ぎしり・食いしばり
歯ぎしりや食いしばりなどの習癖があると、歯と歯ぐきに過剰な負担がかかります。
そうすると、歯の破折や亀裂を招くだけでなく、歯ぐきに炎症をもたらし、歯肉退縮を引き起こすのです。
ちなみに、歯ぎしりによってかかる力は、100kgを超えることも珍しくありません。
原因⑤歯並びやかみ合わせが悪い
歯並びやかみ合わせに乱れがあると、特定の歯や歯茎に過剰な負担がかかります。
そうしたケースでも歯ぐきに炎症反応が生じ、徐々に下がっていってしまいます。
原因⑥矯正治療の影響
歯並びをきれいにする矯正治療においても、歯肉退縮が見られることがあります。
適切な矯正力を働かせている限りは歯肉も退縮しないのですが、装置に不具合が生じて過剰な力が歯ぐきに加わると退縮を引き起こします。
そんな矯正治療による歯肉退縮は、装置を調整することで改善できます。
原因⑦詰め物や被せ物が合っていない
虫歯治療の後に装着した詰め物・被せ物が合っていないケースも注意が必要です。
例えば、被せ物が高すぎると、噛んだ時の力がその歯に集中するため、歯ぐきにダメージが及びやすくなります。
あるいは、被せ物の辺縁が歯ぐきに当たることでも歯肉退縮が起こります。
いずれにせよ、詰め物・被せ物を早急に調整することが大切です。
原因⑧爪を噛む癖がある
普段から爪を噛んでいると、歯ぐきに大きな負担がかかります。
たかが“爪噛み”とは考えず、できるだけ早期に改善するよう努めましょう。
成人してからも爪を噛む癖が残っている人は意外に多いものです。
原因➈元から骨、歯茎が薄い
もともと歯ぐきや顎の骨が薄い人は、歯肉退縮が起こりやすくなっています。
ちょっとした刺激が加わることで歯ぐきがさがってしまいますので十分注意しましょう。
原因➉加齢
歯肉退縮は加齢が原因になることもあります。
歯ぐきもその他の組織・器官と同様、年を重ねるごとに退化したり、委縮したりするものです。
お口の中を常に健康に保つことで、加齢による歯肉退縮の速度は遅らせることが可能です。
原因⑪ホルモンバランス
ホルモンバランスの乱れが原因の歯肉退縮としては、妊娠性歯肉炎が有名です。
妊娠期は女性ホルモンのバランスが崩れ、唾液の分泌量が低下したり、歯周病菌の活動が活発化したりします。
その結果、歯ぐきに炎症が起こって歯肉が退縮します。
原因⑫タバコ
タバコの煙に含まれる一酸化炭素やニコチンは、歯ぐきの血流を悪くし、歯周病のリスクを上昇させます。
また、歯ぐき自体も委縮することで、歯肉退縮が促進されます。
喫煙は、歯ぐきの慢性的な栄養不足・酸素不足をもたらすものだとお考えください。
次回は、歯肉退縮の症状と対策についてのお話です。