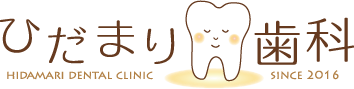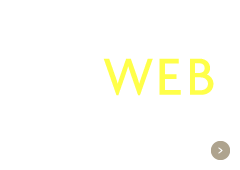歯周病とは?
30歳以上の成人の約80%がかかっていると言われる歯周病。耳にはするけど、どんなものなのか?どうすればいいのか?という疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?
歯周病とはどんな病気?
歯周病とは、細菌の感染によって引き起こされる炎症性疾患で、歯の周りの歯ぐきや、歯を支える骨などが溶けてしまう病気です。
歯と歯肉の境目の清掃が行き届かないでいると、そこに多くの細菌が停滞し歯肉周りが炎症を起こして赤くなったり、腫れたりしますが痛みはほとんどの場合ありません。
さらに進行すると膿がでたり歯が動揺してきて、最後には歯を抜かなければならなくなってしまうのです。

歯周病のセルフチェックをしてみましょう!
1.口臭を指摘された・自分で気になる
2.朝起きたら口の中がネバネバする
3.歯みがき後に、歯ブラシの毛先に血がついたり、すすいだ水に血が混じることがある
4.歯肉が赤く腫れてきた
5.歯肉が下がり、歯が長くなった気がする
6.歯肉を押すと血や膿が出る
7.歯と歯の間に物が詰まりやすい
8.歯が浮いたような気がする
9.歯並びが変わった気がする
0.歯が揺れている気がする
【判定】
チェックが1~3個の場合
歯周病の可能性があるため、軽度のうちに 治療を受けましょう。
チェックが4~5個以上の場合
中等度以上に歯周病が進行している可能性 があります。早期に歯周病の治療を受けましょう。
チェックが0個の場合
チェックがない場合でも無症状で歯周病が進行することがあるため1年に1回は歯科検診を受けましょう。
歯周病の原因
お口の中にはおよそ400~700種類の細菌が住んでいると言われています。
これらは普段あまり悪いことをしませんが、ブラッシングが充分でなかったり、砂糖を過剰に摂取すると細菌がネバネバした物質を作り出し、歯の表面にくっつきます。
これをプラークと言い、粘着性が強くうがいをした程度では落ちてはくれません。
このプラーク1mgの中には約10億個の細菌が住みついていると言われ、むし歯や歯周病をひき起こすのです。その中でも、歯周病をひき起こす細苗が多く存在していと言われています。
このプラークの細菌によって歯肉に炎症をひき起こし、やがては歯を支えている骨を溶かしていく病気のことで、結果的に歯を失う原因となるのです。
プラークは取り除かなければ硬くなり、歯石と言われる物質に変化し歯の表面に強固に付着します。これはブラッシングだけでは取り除くことができません。この歯石の中や周囲に細菌が入り込み、歯周病を進行させる毒素を出し続けていきます。
次のことも歯周病を進行させる原因となります。
・糖尿病
・喫煙
・歯ぎしり、くいしばり、かみしめ
・不適合な冠や義歯
・不規則な食習慣
・ストレス
・全身疾患(糖尿病、骨粗鬆症、ホルモン異常)
・薬の長期服用
・部分的に歯がない(歯がある方で噛むため負担が増加し、歯周病を部分的に進行する)
・両親が若い時から入れ歯だった
・口で呼吸することが多い
・免疫抑制剤をに飲んでいる、あるいは免疫低下の状態
このような方は歯周病になりやすいあるいは進行が速い傾向にあるため、歯医者さんに相談してみましょう。
歯周病って治るの?
現在では歯周病は、予防でき治療も可能です。 大切なのは予防、診断、治療、そしてメンテナンスです。
近年、歯周治療は急速な進歩を遂げています。以前は「不治の病」とさえ言われていた歯周病も、現在では進行を阻止することが可能となり、健康をとりもどすことができるのです。まず、歯周病の原因はプラークですから、それをためない、増やさないことが基本です。
そのためには・・・
・正しい歯ブラシの方法で毎日歯みがきすることです。歯の表面を歯垢のない清潔な状態にしておく事が何より大切です。
・歯肉の中まで入っている歯石を取り除き、さらに根の表面を滑らかにして炎症を引き起こす細菌を徹底的に除去すること。
・傷んだ歯肉、骨を治療して健康に近い歯肉にすること。
・健康の保持のため歯科衛生士による専門的なクリーニングなどのメインテナンスを定期的に受けること。
歯肉の炎症が全身に多くの影響を及ぼすことは昨今の研究で明らかになってきています。歯周病も糖尿病も生活習慣病ですから互いに深い関係があって不思議ではないのです。
毎日の食生活を含めた生活習慣を見直し、歯周病を予防する事が全身の生活習慣病を予防することにつながります。
歯医者さんはお口の中の変化をみるプロです。口腔ケアも自分一人できちんと行うのは難しいと思います。
半年に一度は歯医者さんを受診して、生活習慣も含め口腔内のケアを受けるようにしましょう。