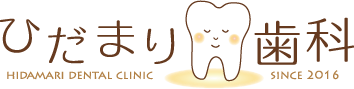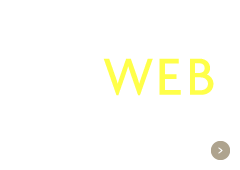- 9:00-13:00/14:00-18:00
- 休診/祝日
阿倍野区昭和町駅の歯医者 ひだまり歯科のスタッフブログ
受け口は歯科用語で反対咬合と言い、不正咬合の一種であり、上顎よりも下顎の方が前方へ突出した状態を指します。
口を「イー」としたときに、上の前歯よりも下の前歯が前に出ている状態だったら、反対咬合(受け口)と判断できます。
反対咬合になる3つの原因
原因1 親からの遺伝
顔や声がお子様に遺伝しやすいように、歯並びや骨格も遺伝します。親が反対咬合だから必ず遺伝するというわけではありませんが、
両親どちらかが受け口の場合は、お子様もその骨格を受け継ぐ場合があります。
また、遺伝だけでなく親御さんの癖をお子様が真似をして、それが反対咬合の原因になることも
原因2 幼少期の癖
幼少期の子どもの顎の骨は柔らかいため、唇を吸う癖や頬杖、顎を前に出す仕草が癖になっている場合、反対咬合を引き起こす原因となることもあります。
癖は長く続くにつれて、やめさせることが難しくなる場合もあり、反対咬合を進行させてしまう可能性もあるため、早い段階でやめさせるようにしましょう。
原因3 下の顎の過成長
成長過程で、上の顎よりも下の顎が発達し、大きくなってしまい、反対咬合になる場合もあります。
上の顎と下の顎のバランスがわるく成長してしまう原因の一つとしては、舌の位置が関係してることもあります。舌の正しい位置は、
上の顎にくっついており、支えてる状態が望ましいのですが、何らかの理由で舌が下がってしまっていると、下の顎が発達してしまうこともあります。
反対咬合の治療方法
反対咬合の治療は、歯並びと骨格のどちらの要因によるものなのかで選択肢が違ってきます。
また治療を始める年齢によっても治療方法が変わります。
幼少期であれば、骨格的な要因であっても、発育・成長を利用して矯正装置によって改善できる場合があります。
小児矯正の年齢は通常6歳以降の混合歯列期(乳歯と永久歯が混ざった状態の時期)に始めるのが一般的ですが、反対咬合に限っては、
3歳ぐらいからマウスピースを使った治療が有効的です。
すでに発育・成長が終わっている成人であれば、歯列矯正による治療となりますが、原因が骨格的な問題であれば外科手術を伴う治療が必要になる可能性があります。
<受け口の改善は相談から始めましょう>
反対咬合は、審美的な問題やコミュニケーションの問題から、コンプレックスに感じてしまうことが多い噛み合わせです。
中には、その見た目や発音をからかわれるという経験を持つ方も多くおられます。
しかし、なかなか治療に踏み切れなかったり、費用面で気になったり、噛み合わせが変わることの不安もあると思います。
ですから、まずは「治療する」と意気込むのではなく、相談のつもりで歯科をご利用いただければと思います。
反対咬合は決していい噛み合わせではありません。将来的に身体や歯にどのような影響が現れるのか、治療するとすればどんな治療で
どのくらいの費用や期間がかかるのか、相談してから治療するかどうかを決めましょう!